近年、家電や化粧品、ブランド品などで「並行輸入品」と表示された商品を見かける機会が増えてきました。
価格が安く、国内で入手困難な製品も手に入るため注目される一方、「品質は大丈夫?」「保証はあるの?」といった疑問や不安を持つ方も多いでしょう。
本記事では、「並行輸入品とは何か」という基本から、正規輸入との違い、メリット・デメリット、取り扱いに関する法律、そして購入・販売時の注意点までを、図表を交えながらわかりやすく解説していきます。
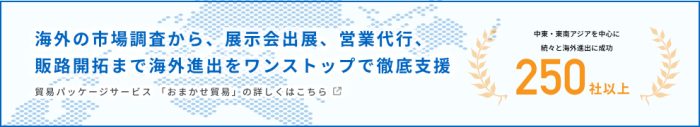
並行輸入品とは?―正規輸入品との違いをわかりやすく解説

「並行輸入品」という言葉は、家電量販店やECサイトなどで目にする機会が増えていますが、その意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。並行輸入品の定義と、正規輸入品との構造的な違いをわかりやすく解説します。
並行輸入品とは何か?
並行輸入品とは、メーカーの正規代理店を通さず、第三者が独自に海外から直接輸入した正規品のことです。ここで重要なのは、「正規ルート外」であるだけで、商品自体は本物であるという点です。偽物や海賊版とは明確に区別されます。
たとえば、海外の正規販売店で販売されているブランドバッグや腕時計を、個人や業者が日本に輸入して販売した場合、それは並行輸入品に該当します。
日本のメーカーや公式代理店を介していないため、輸入経路が“並行”しているという意味でこのように呼ばれます。
正規輸入品との輸入ルートの違い
並行輸入品と正規輸入品では、以下のように「誰がどのルートで輸入するのか」「どんな契約関係があるのか」によって構造が異なります。
輸入ルートの比較表
| 項目 | 正規輸入品 | 並行輸入品 |
|---|---|---|
| 輸入者 | メーカーと契約した 正規代理店 |
非正規の 輸入業者・個人 |
| 契約関係 | メーカーと 販売契約を締結 |
契約なし (買付のみ) |
| 商品の出所 | メーカーが指定した販路 | 海外市場の 一般流通ルート |
| アフターサポート | メーカーの正規保証あり | 保証対象外または限定的 |
| 商品の識別 | 国内仕様 (説明書・ラベル等) |
海外仕様 (外国語表記含む) |
正規輸入品は、メーカーが輸出前に国内向けの仕様に調整しているため、マニュアルが日本語であったり、技適マーク(電波法適合)が付いていたりすることが多く、ユーザーにとって安心感があります。
一方、並行輸入品は、現地仕様のままで販売されるため、取扱説明書が英語・中国語のみだったり、日本の電源規格に対応していない電化製品があったりと、使い勝手に影響を及ぼすケースもあります。
なぜ並行輸入品が流通するのか?
そもそも、なぜ正規ルート以外のルートで商品が流通しているのでしょうか?
その背景には以下のような事情があります。
・価格差を活用したビジネス
為替の差や現地市場との価格差を利用し、より安く仕入れて国内で利益を出す手法。
・国内未発売商品への需要
国内市場では入手できない製品(色、サイズ、限定モデルなど)を求めるユーザーが存在。
・ECサイトや越境ECの普及
インターネットの発展により、海外の消費者向け商品が誰でも購入・輸入しやすくなった。
これらの要因により、小売事業者だけでなく個人輸入者や副業層からも並行輸入は注目されており、日本国内での流通量も年々拡大しています。
なぜ選ばれる?並行輸入品の4つのメリット

並行輸入品には、正規代理店を通さないがゆえの多くの利点があります。特に「価格」「入手可能性」「販売戦略の自由度」といった面で魅力が大きく、消費者にも事業者にも選ばれる理由が明確です。
この章では、並行輸入品ならではの4つの主要なメリットを詳しく解説します。
1.価格が安い
並行輸入品の最大の魅力は「価格が安くなる可能性が高い」という点です。メーカーとの契約に基づかないルートでの仕入れであるため、中間マージンが省かれ、販売価格に柔軟性を持たせることができます。
また、現地での販売価格や為替レートの変動を活用すれば、国内正規品と比べて10〜30%以上安くなるケースも珍しくありません。
並行輸入による価格差の例
| 商品カテゴリ | 正規価格 | 並行輸入価格 |
|---|---|---|
| 高級腕時計 | 約75万円 | 約59万円 |
| ブランド香水 | 約15,000円 | 約9,800円 |
| 海外イヤホン | 約38,000円 | 約28,500円 |
※2025年5月時点の市場価格をもとに一例を示しています。
2.国内未発売品・限定モデルが手に入る
並行輸入品は、日本では手に入らないモデルやカラー、仕様の商品を購入できる点も大きな魅力です。
たとえば、海外限定のスニーカー、欧米仕様のコスメ、海外向け電子機器など、“日本にないもの”が買える希少性があります。
代表的な事例
・海外限定カラーのスニーカー(NikeやAdidasの地域限定モデル)
・欧州仕様のDiorコスメ(国内とは成分や色展開が異なる)
・Amazon Echo英語版(国内未対応サービス向け)
こうした商品はファッション性や個性を重視する層に人気が高く、また事業者にとっては競合との差別化にもつながります。
3.販売の自由度が高い(事業者視点)
事業者側にとってのメリットとして重要なのが、「販売戦略の自由度が高い」ことです。並行輸入品はメーカーとの契約がないため、以下のような柔軟な販売戦略が可能になります。
・価格設定を自由に決められる
・取り扱い商品を自社の裁量で選べる
・国内での独自ブランド構築や販促施策がしやすい
たとえば正規代理店として契約していると、「希望小売価格から値下げNG」「特定販路のみでの販売」などの縛りが発生することもありますが、並行輸入であればそれらの制約を回避できます。
これは小規模ECサイトや新規参入企業にとって、大きな差別化ポイントとなります。
4.インバウンド需要や外国人向けに対応しやすい
近年、日本を訪れる外国人観光客が増える中、母国仕様の商品を求める声も増加しています。たとえば、
・英語や中国語表記のパッケージ
・海外の電圧・コンセント対応製品
・自国で使い慣れたブランド製品
など、並行輸入品であれば外国人のニーズに合った商品を提供しやすくなります。これはインバウンド消費を意識した小売戦略でも有効です。
並行輸入品は、単なる“安さ”だけでなく、「ここにしかない」「自由に売れる」「他と違うものがある」という多面的なメリットによって選ばれています。
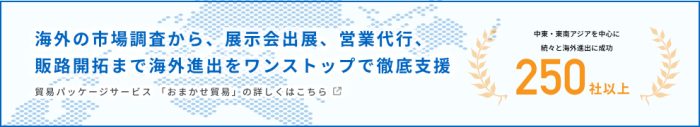
注意が必要!並行輸入品のデメリットと3つのリスク

並行輸入品には価格面や商品ラインナップの面で多くのメリットがありますが、同時に見過ごせないリスクも存在します。特に「保証・アフターサービスの対象外」「偽物の可能性」「日本国内での使用・販売の難しさ」などは、購入前にしっかり理解しておくべき注意点です。
1.メーカー保証やサポートが受けられないことが多い
最も大きなリスクは、「メーカーの正規保証が適用されない」ケースが多いことです。
並行輸入品は正規代理店を通っていないため、初期不良や故障時に国内メーカーの無償修理や交換対応が受けられない場合があります。
保証面の違い(例)
| 項目 | 正規輸入品 | 並行輸入品 |
|---|---|---|
| 保証書の有効性 | 国内保証対象 | 保証外または要確認 |
| 修理対応 | メーカー対応 | 拒否・有償になる場合あり |
たとえばApple製品や一部の家電ブランドは、並行輸入品に対して保証対象外と明記しています。購入前に「どこが保証してくれるのか」「修理はどうなるのか」を確認する必要があります。
2.偽物・模倣品のリスクがある
並行輸入品は正規品であることが前提ですが、海外からの個人・業者経由の取引では、偽物や再整備品(リファービッシュ)を掴まされるリスクもゼロではありません。
特にリスクが高いのは以下のような商品ジャンルです。
・高級ブランド品(腕時計、バッグ、財布など)
・化粧品・香水(成分不明・パッケージ類似)
・電子機器(見た目は本物でも中身が粗悪品)
偽物対策のチェックポイント
購入時には、以下のような点を確認することが重要です:
・商品の型番・JANコードが正規品と一致しているか
・販売者の会社概要・所在地・連絡先が明示されているか
・極端に安すぎる価格設定ではないか(相場からの乖離)
また、国民生活センターなどの公的機関も、並行輸入に絡むトラブルについて注意喚起を行っています。「安すぎる並行輸入品」には慎重な姿勢が必要です。
3.日本国内での仕様違い・使用制限がある
並行輸入品は、日本向けにカスタマイズされた商品ではないため、技術仕様や使用環境が日本国内と異なることがあります。これにより、以下のような問題が発生します:
・電化製品が日本の電圧(100V)に対応していない
・説明書が英語や中国語で日本語版が同梱されていない
・日本国内の技適マーク(無線機器)を取得していない
使用時のリスク一例
| リスクの種類 | 内容例 |
|---|---|
| 電気的リスク | 海外電圧用家電の誤使用による発火・故障 |
| 法的リスク | 技適マークなし機器の使用で電波法違反 |
| 利便性低下 | 日本語マニュアルがない・保証書無効 |
とくに無線機器(Bluetoothイヤホン、Wi-Fiルーターなど)については、「技適マーク」がないと日本国内での使用が電波法により制限されます。輸入・販売は合法でも、使用そのものが違法となるケースもあるため注意が必要です。
並行輸入品は一見お得に見えても、保証が効かない、修理できない、偽物だった――といった事態が発生すると、かえって損失につながることもあります。
購入や販売を検討する際には、保証やアフターサービスはどうなるか?、商品仕様は日本で使用可能か?、信頼できる仕入先・販売元か?のような判断軸が求められます。
並行輸入品の取り扱いに関する法律と実務知識

並行輸入は違法ではなく、日本の市場でも合法的に取引されています。しかし、商標権や電波法、税関での差止めなど、一定の条件を満たしていなければ法的トラブルに発展するリスクがあります。
並行輸入は合法だが「条件付きの合法」
日本において並行輸入が認められている根拠は、知的財産権の一種である商標権に関する「消尽理論」です。
この理論に基づき、商標権者が海外で正当に販売した商品であれば、第三者が日本に輸入・販売しても商標権侵害にはならないとされています。
並行輸入の合法性(基本パターン)
| ケース | 商標権の関係 | 輸入可否 |
|---|---|---|
| 海外で正規に販売された商品を、 日本でも同一商標権者が管理している |
同一商標権者 | 原則OK |
| 海外と日本で異なる会社が 商標権を保有している (ライセンス関係が異なる) |
商標権者が異なる | NGになる 可能性あり |
| 海外製品が日本の安全基準、 技術基準に適合していない |
要件を満たさない | NGまたは要確認 |
したがって、「どこで作られた商品か」だけでなく、「誰が商標を持っているか」も重要なチェックポイントになります。
税関での差止め対象となるケース
並行輸入品の輸入時には、商標権者からの申請によって税関で差止め(ストップ)されることがあります。とくに次のような状況では、輸入そのものが禁止される可能性があります。
・日本国内の商標権者と海外の製造者が別企業
・商品に偽装がある、正規ルートとの混同を招く表示がある
・安全基準を満たしていない製品(食品、化粧品、医療機器等)
税関で差し止められると、輸入者は商品の正当性を証明するために、製造元や販売元との関係性を示す書類提出を求められることがあります。それができない場合、商品は廃棄または返送されます。
税関差止めに関する実務ポイント
・商品のブランドや型番が商標権の対象になっていないか事前確認
・輸入前に「知的財産情報データバンク(INPIT)」で商標の出願状況を確認
・商品の説明書やラベルに誤解を招く表記(「正規品」「日本向け」など)を避ける
その他の法的留意点(技適・薬機・食品表示法など)
商標以外にも、製品ジャンルごとに以下のような法律が適用されます。並行輸入を事業として行う場合は、輸入対象商品の法規制を正確に把握することが不可欠です。
| 対象商品 | 適用される法令 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 無線機器 | 電波法(技適) | 技適マークがないと 使用不可(販売は可) |
| 化粧品・医薬部外品 | 薬機法 | 成分表示義務・届出制 未承認成分NG |
| 食品・サプリ | 食品衛生法・食品表示法 | 添加物や栄養表示の 適合性が求められる |
違反すると、販売停止・行政指導・罰則対象になる可能性があるため、特に初めて並行輸入を行う事業者は、税理士や通関士、行政書士などの専門家への相談を推奨します。
個人輸入と事業者輸入の違い
一般消費者が「個人で使用する目的」で海外から商品を購入する場合(個人輸入)と、販売目的で仕入れる事業者輸入とでは、適用される規制や責任の重さが異なります。
| 比較項目 | 個人輸入 | 事業者輸入 |
|---|---|---|
| 輸入目的 | 自己使用 | 転売・販売 |
| 表示・規制対応 | 原則不要 | 法令遵守が義務(成分表示など) |
| トラブル対応責任 | 自己責任 | 消費者保護・PL法の対象となる |
たとえば化粧品やサプリメントでは、同じ商品でも個人輸入はOKだが、事業者としての販売はNGというケースもあるため要注意です。
並行輸入は商標や技術基準に適合していれば合法ですが、細かな要件を知らずに輸入・販売を行うと、思わぬ差止めや行政処分につながるおそれがあります。
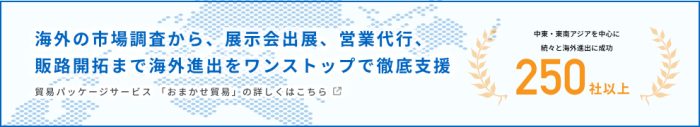
まとめ
並行輸入品は、メーカーの正規代理店を通さずに輸入される正規品であり、価格面や希少性の面で大きな魅力を持っています。国内では流通していない限定モデルや、正規ルートよりも安価な価格設定が可能な点から、多くの消費者や事業者に支持されています。
一方で、並行輸入品にはいくつかの見逃せないリスクも存在します。また、技術基準や法律への適合性が問われるケースも多く、たとえ本物であっても使用や販売に制限がかかることがあります。
並行輸入品を選ぶ際には、価格や希少性といった表面的なメリットだけに目を向けるのではなく、自分が求めるサポートや使用環境に適しているかを冷静に見極めることが重要です。
正しく理解し、リスクとメリットのバランスを踏まえた上で賢く選ぶことで、並行輸入品は非常に有効な選択肢となり得ます。特に、海外製品への関心が高まる今こそ、その正しい知識と判断が求められています。




